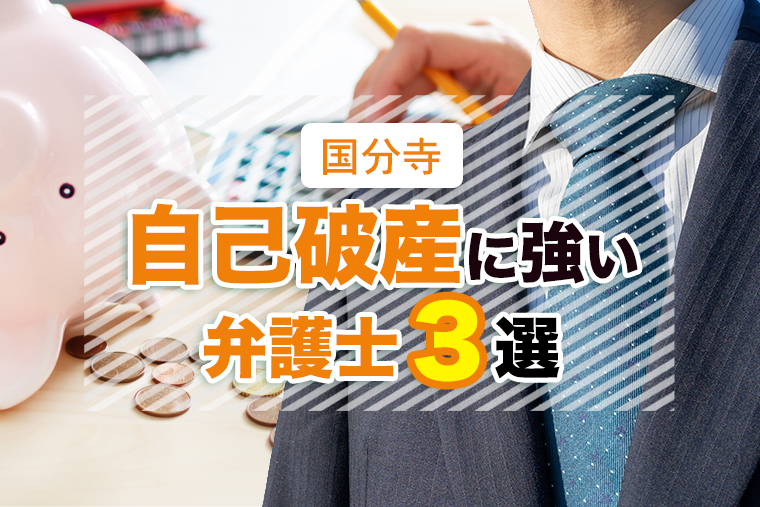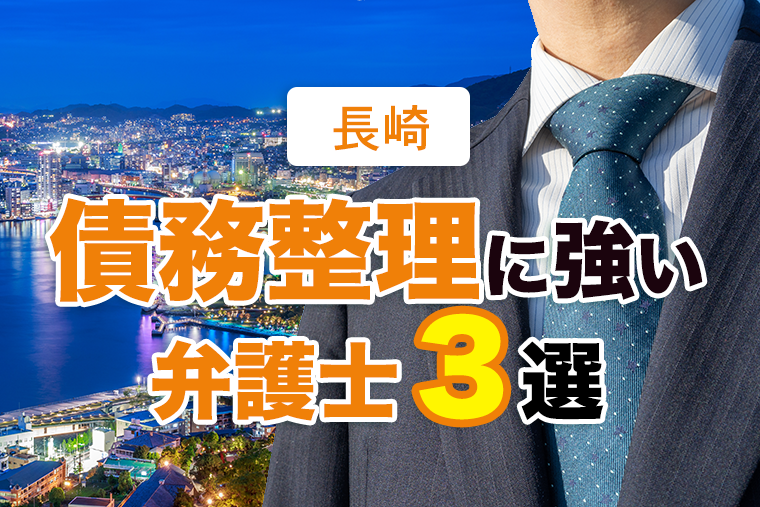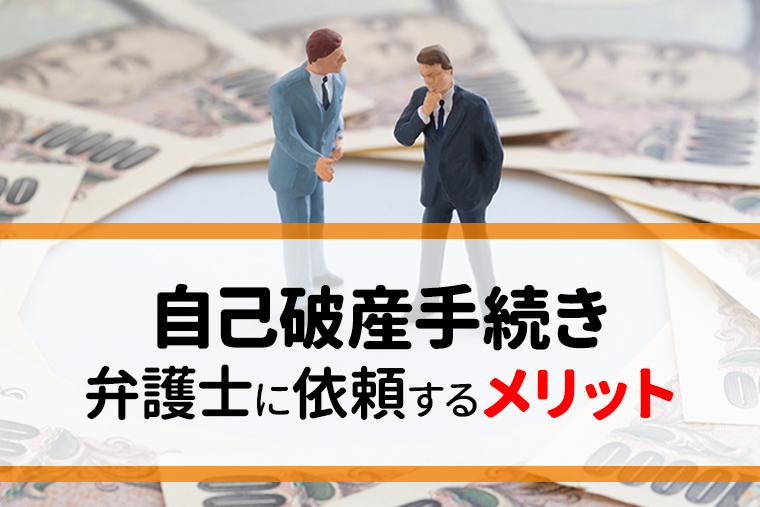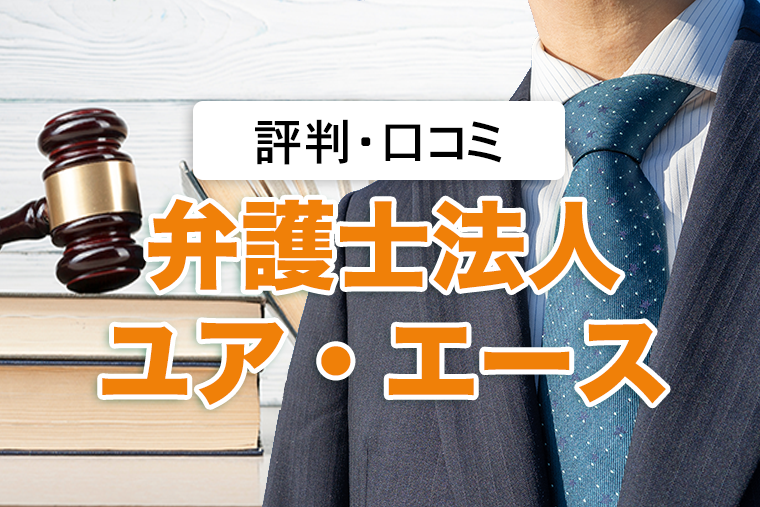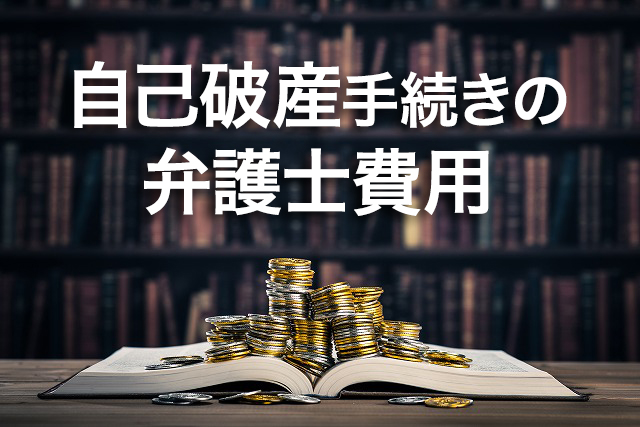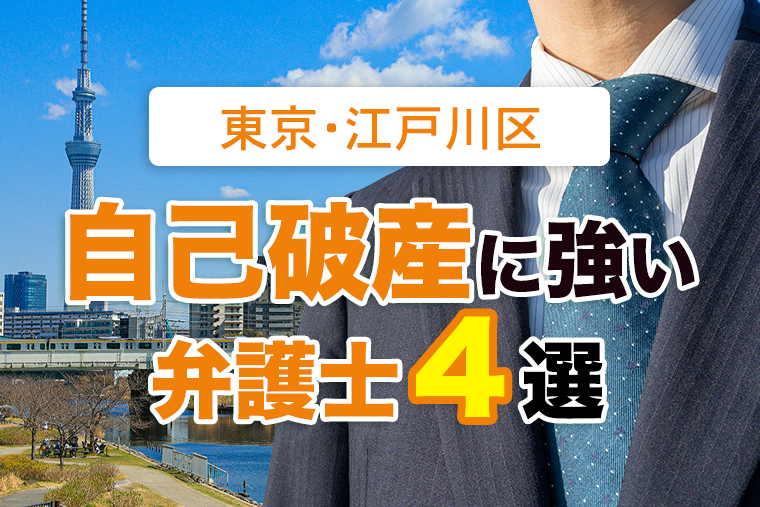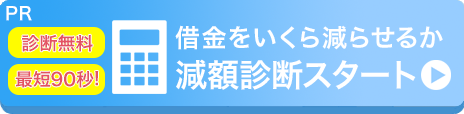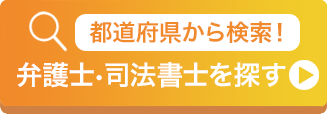弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所の破産でお困りの依頼者様へ

2020年6月24日、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が東京地裁から破産手続き開始決定を受けたことは、異例のニュースとして広く知られています。この法律事務所はかつて、過払い金返還請求などを主に取り扱っており、多くの方がテレビCMなどでその名前を聞いたことがあるかもしれません。
弁護士法人が大きな負債を抱えて破産する事態は、社会的な注目を浴びる出来事です。特に、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所に依頼をしていた方々にとっては、以下のような疑問が生じることでしょう。
- 委任契約はどうなるのか?
- 支払った依頼費用は返金されるのか?
- 回収された過払い金は返還されるのか?
こうした疑問に対して、弁護士が詳細な解説を行います。ご依頼者の皆様にとって気になる点に対して、適切な情報を提供し、不安を解消するお手伝いをいたします。
目次
弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所の破産による依頼者への影響
弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所の破産によって、実際に依頼をしていた方にはどのような影響が及ぶのでしょうか。
委任契約は終了される
依頼者の方は、弁護士に事件処理を依頼する際、委任契約を締結します。
もし事件が未処理で委任契約が続いている場合には、破産管財人により、委任契約が終了されます(破産法53条1項)。
そのため、依頼者の方が引き続き事件を処理してもらうことを希望する場合には、別の弁護士に依頼をする必要があります。
未着手または途中終了の場合、支払い済みの着手金は返してもらえる?
たとえば過払い金返還請求や債務整理を依頼して、着手金を支払った状態で弁護士法人が倒産してしまった場合、支払い済みの着手金はどうなるのでしょうか。
この場合、既に解説したとおり、委任契約は破産法53条1項の規定に従い、破産管財人により解除されることになります。
このとき、支払い済みの着手金は「破産者の受けた反対給付」(破産法54条2項)に該当します。
したがって、着手金に相当する金銭が破産財団(破産手続開始の時点で弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が所有する財産)中に現存する場合には、同規定に基づき、その返還を請求することができます。
しかし、同じような立場の依頼者が複数いることが予想されますので、破産財団がすべての依頼者に着手金を返還するには足りなくなるかもしれません。
その場合は、破産手続の中で「財団債権」として弁済されることになります。
財団債権とは、破産手続を進めるためにかかる費用(手続き費用や破産管財人報酬など)の次に弁済を受けられる債権のグループで、一般の破産債権よりも優先的に支払いを受けることが可能です。
ただし、破産財団が不足して財団債権の全額を支払うことができない場合には、債権額に応じて各財団債権者へ按分弁済が行われます。
回収済みの過払い金は返してもらえる?
既に貸金業者から過払い金の回収を済ませた状態で、弁護士法人が破産した場合、回収済みの過払い金は消費者に返してもらえるのでしょうか。
この場合の過払い金は、本来消費者のものであるところを弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が預かっているに過ぎないので、破産財団には含まれません。
したがって、消費者は弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(破産管財人)に対して、回収済みの過払い金全額の返還を請求することができます(破産法62条、取戻権)。
なお、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が回収済みの過払い金を使い込んでしまい、もはや金銭が残っていないという場合には、回収不能となった分は消費者の損害となります。
この損害賠償請求権は「破産債権」となり、一般の債権と同様に破産手続の中で配当を受けます。
しかし、回収済みの過払い金を支払えない状況では、配当を受けられる可能性は極めて低いと考えられます。
他の弁護士に依頼するための費用を賠償してもらえる?
弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所との委任契約が解除され、事件の処理を別の弁護士に依頼しなければならなくなり、余分な費用がかかってしまった場合には、その費用分は消費者の損害となります。
委任契約の解除に伴う損害賠償請求権は「破産債権」となり、一般の債権と同様に破産手続の中で配当を受けることができます。
しかし、破産手続の費用や財団債権の弁済などで破産財団がほとんどなくなってしまう可能性も高いため、配当を受けられる可能性は低いでしょう。
任意整理の分割返済を依頼していた場合は、早急に債権者へ連絡
債務整理のうち、任意整理を弁護士に依頼した場合、債権者に対する分割返済を弁護士を通じて行うケースがあります。
弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所に任意整理の分割返済を依頼していた場合、破産により業務が停止して、分割返済が滞ってしまいます。
分割返済の履行遅滞が数ヶ月間続くと、借金の残額を一括で返済することを求められてしまいますので、早急に対処が必要です。
一刻も早く債権者に連絡をして、支払い方法の変更を依頼し、自ら直接債権者に対して分割返済を行うようにしましょう。
その場合であっても、まず他の弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所の弁護士は責任を負うのか?
弁護士法人が破産して、着手金や回収済みの過払い金を弁護士法人から回収できなくなってしまった場合、弁護士個人に対して回収不能分を請求することはできるのでしょうか。
弁護士法人所属の弁護士は無限責任を負う
弁護士法人は、社員である弁護士※1により構成された法人です。
これは、弁護士法人の社員の「無限責任」を定めた規定です。
したがって、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所の依頼者の方が着手金や回収済みの過払い金を回収できなくなった場合、社員である弁護士に対して回収不能分を請求することができます。
※1 弁護士法人の場合も、組合である法律事務所と同様、出資をせずに雇われているだけの弁護士(アソシエイト弁護士、イソ弁等)も存在します。
このような、いわゆる「雇われ弁護士」は、弁護士法上の「弁護士法人の社員」ではないので、無限責任の対象外です。
退社したとしても、退社登記完了時点までの債務について責任を負う
仮に、「社員である弁護士」が、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所を退社した場合であっても、社員であった間に弁護士法人が負担した債務の無限責任を免れることはできません。
弁護士法30条の15第7項が準用する会社法612条1項によれば、退社した社員は、退社の登記をする前に生じた弁護士法人の債務について、引き続き無限責任を負担します。
つまり、依頼者の方が着手金を支払った時点、過払い金を回収した時点において社員であった弁護士に対しては、回収不能分を直接請求することができます。
弁護士個人が破産してしまった場合は?
弁護士個人が破産してしまった場合、弁護士個人への請求はできなくなってしまうのでしょうか。
この点、弁護士個人に対する請求権は、破産手続内で破産債権として取り扱われ、一般の債権と同様に配当を受けることになります。
そして、最終的には免責が認められ、それ以上弁護士個人に対する請求はできなくなるのが原則です。
しかし、弁護士個人が悪意による不法行為を働き、その行為によって依頼者が損害を被った場合には、例外的に免責が認められません(破産法253条1項2号)。
よってこの場合には、破産手続終了後でも、弁護士個人に対して債務の履行を請求することができます。
依頼者の方が取るべき対応方法は?
弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所の破産により影響を受けてしまった依頼者の方は、どのような対応を取るべきなのでしょうか。
まず、東京ミネルヴァ法律事務所の破産手続きに関する情報及び破産管財人のホームページをご参照ください。また、東京ミネルヴァ法律事務所被害対策全国弁護団では、相談フォームも設置してありますので、こちらに相談してみるとよいでしょう。
破産管財人室
時間帯 月曜~金曜(祝日を除く) 午前10時~12時および14時~16時
参考外部サイト(東京第一弁護士会):「弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所 破産管財人HP」
東京ミネルヴァ法律事務所被害対策全国弁護団について
「東京ミネルヴァ法律事務所被害対策全国弁護団」は、東京ミネルヴァ法律事務所に事件を依頼していた方々等の被害救済を目的として、全国の弁護士有志により結成された弁護団です。
同弁護団では、継続中の事件についての相談(弁護士の紹介)、破産債権届出業務の受任を行っていますので、これらについてお困りの方は、同弁護団にご相談ください。
未処理の事件については他の弁護士に依頼する
未着手のまま、あるいは途中までしか事件処理が終わらないままに弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所との委任契約が解除されてしまった場合は、完了していない事件の処理を他の弁護士に依頼しましょう。
また一からの相談になってしまいますが、やむを得ません。
後任の弁護士には、事件がどこまで進んでいるかも含めて、詳しく事情を説明して事件処理に当たってもらいましょう。
退社した元所属弁護士への依頼は注意が必要
依頼者の方としては、これまで事件を処理してくれていた弁護士に引き続き依頼をするのが良いのではないかと考えるかもしれません。
しかし、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所を退社した弁護士に再び依頼することは注意が必要です。
理由は以下のとおりです。
①懲戒処分により業務停止となる可能性がある
弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が今回の破産に関連して行っていた行為は、弁護士会から問題視されている部分※2があり、今後弁護士会によって懲戒処分が行われる可能性があります。
今回の事案の規模に鑑みると、懲戒処分の中でも重い業務停止処分に処せられる可能性も高く、その場合はまた別の弁護士を探さなければなりません。
弁護士法人内での役割やオペレーション次第では、代表のみならず雇われ弁護士に対しても懲戒処分が行われる可能性は否定できません。
二度手間・三度手間になることを防ぐためにも、退社した弁護士への依頼は、弁護士会の相談窓口とも相談した上で、注意深く判断したほうがよいでしょう。
すでに引継ぎ処理がされている方は、引継ぎの際、依頼者に十分な事前説明がなされたのか、法的に有効な形で行われたのか、弁護士会の相談窓口にあわせて問い合わせてみるとよいでしょう。
※2 参考外部サイト:「当会所属の弁護士法人に関する会長談話」(東京第一弁護士会公式サイト)
抜粋:「引き続き当会は、速やかに事案を解明し、同法人及び代表弁護士等の関係者に対して、懲戒請求をはじめとする厳正な対応を行う所存です。」
なお、弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(弁護士法57条1項)。
- 戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
- 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
- 退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
- 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)
参考:日本弁護士会連合会「懲戒制度の概要」
②弁護士個人に対する請求を行う余地もある
既に解説したとおり、弁護士法人から回収不能となった金銭を「社員であった弁護士」個人に対して請求することも考えられます。
請求の相手方になる可能性がある弁護士に事件処理を依頼することは好ましくないでしょう。
弁護士法人や(元)所属弁護士個人に対する請求を行う
弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所から返してもらうべきお金(着手金や回収済みの過払い金など)がある場合には、弁護士法人や(元)「社員である弁護士」個人に対する請求を行いましょう。
請求を行う際には訴訟になる可能性が高いため、当初から弁護士に依頼をして、手続きを進めることをおすすめします。

診断後は何度でも相談無料
診断後は何度でも相談無料
弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が破産した理由とは?
最後に、そもそも、なぜ弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が破産したのでしょうか?その理由は、正確なところは内部の人間でなければわからないため、推測の域を出ません。
しかし、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所はいわゆる「過払い金バブル」で急成長した事務所として知られています。
グレーゾーン金利
以前の日本では、消費者に対する貸付の利息に関して、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律において規定される上限金利が異なっていました。
利息制限法では年15~20%が上限とされているのに対して、出資法の上限金利は29.2%とされており、この差は「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。
グレーゾーン金利は、利息制限法上は原則無効であったものの、債務者が任意に支払った場合には、その返還を請求することができないとされていました。
このことを利用して、多くの貸金業者がグレーゾーン金利での貸付を行っていた実態が存在しました。
しかし、裁判所は多くの消費者がサラ金などの貸金業者に搾取されている現実を問題視し、判例実務においてグレーゾーン金利を排除していきました。
そして、2010年の出資法改正によりグレーゾーン金利は完全に撤廃されました。
過払い金バブルによる弁護士事務所の拡大
利息制限法の上限を超えるグレーゾーン金利(過払い金)については、判例上貸金業者が利用者に対して返還しなければならないとされています。
これは確立した実務であるため、弁護士事務所にとってはあまり手間をかけることなく、比較的容易に請求を行うことが可能でした。
一方でグレーゾーン金利の被害に遭った消費者は非常に多かったため、過払い金返還請求に特化した弁護士事務所には、短期間に案件を大量に受注し、一気に拡大を見せたところもありました。
過払い金バブルの収束と弁護士事務所の経営悪化
最高裁の判例が固まり、出資法が改正されるまでの2006年から2010年にかけて、グレーゾーン金利での貸付は急激に減少し、2010年以降は全く行うことができなくなりました。
グレーゾーン金利時代に行われていた貸付についての過払い金返還請求案件は引き続き存在しましたが、案件数は次第に減少していきました。
これに対して、過払い金返還請求に特化した法律事務所は、宣伝広告のための広告費や、事務処理要員を雇用するための人件費をかける高コスト体質からなかなか脱却することができません。
このような理由から、過払い金バブルの収束に伴って経営が悪化してしまった弁護士事務所も一定数存在します。
あくまでも推測の域を出ませんが、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が破産した理由も、上記のようなものであったと考えられます。
まとめ
依頼先の弁護士事務所が破産してしまい、驚きを隠せない依頼者の方もいらっしゃるかもしれません。
まずは落ち着いてどのような対応を取るべきなのか、弁護士法人や弁護士個人から返してもらえるお金はあるのかを適切に見極めましょう。
少しでも不安に思うことがあれば、弁護士に相談して対応を検討することをおすすめします。