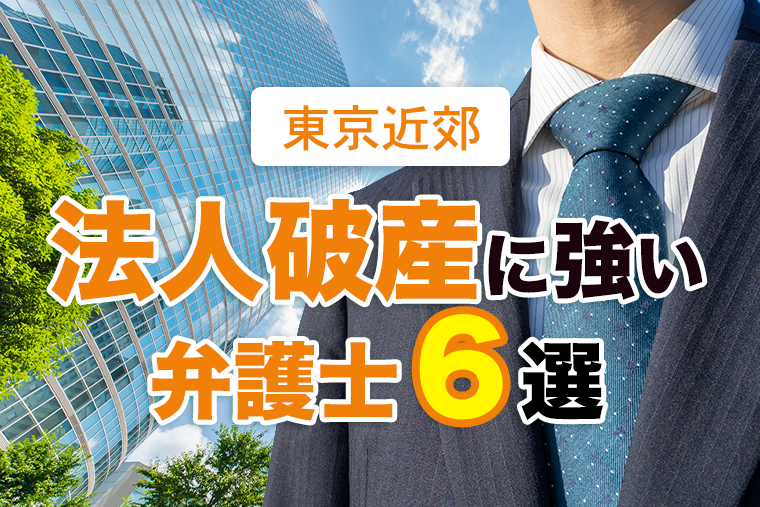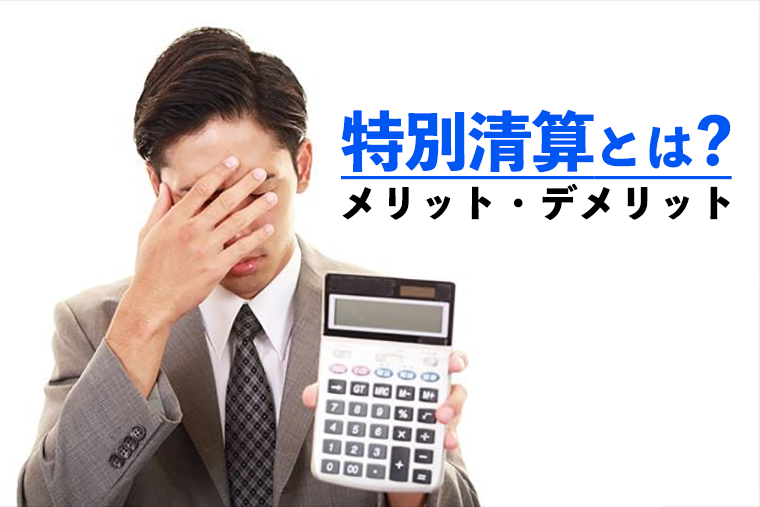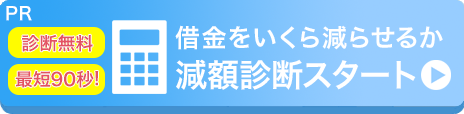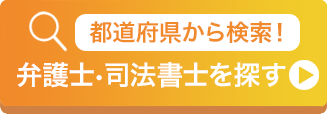会社更生とは?手続きの流れ、メリット・デメリット、民事再生との違い
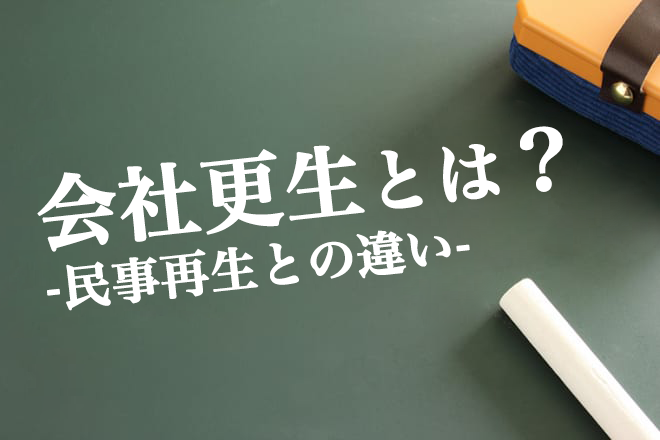
- 会社更生と何でしょうか?
- 会社更生の手続きの流れ、メリット・デメリットを知りたい
大規模な株式会社が経営困難に陥り、財務状況が深刻化した場合、最適な選択肢として「会社更生」手続きが考えられます。
会社更生は非常に強力な手続きですが、一方で信用や費用の側面でデメリットも存在します。会社更生を申し立てる前には、弁護士に相談し、熟考を重ねてから判断することが重要です。
この記事では、会社更生手続きの進行手順について詳しく説明し、民事再生手続きとの違いや、会社更生のメリット、要件、手続きのステップなどを解説します。
目次
会社更生とは?
会社更生とは、財務状況が悪化して窮境に陥った株式会社を存続・更生させるための手続きです。
会社が法人破産に追い込まれた場合、債権者は会社財産の換価処分代金から配当を受けられます。
しかし実際には、法人破産せざるを得ない会社にほとんど財産は残っておらず、債権者は微々たる配当しか受け取ることができません。
そうなる前に、会社の債務を減額するなどして財務状況を改善し、会社を立ち直らせた方が、債権者の回収額は増える可能性があります。
債務の減額等を行うためには、原則として債権者の同意が必要です。
しかし、債権者が多数の場合には、一部の債権者が反対した結果、効果的に債務の減額等を行えないことも考えられます。
このような状況を解決するために有効となるのが、会社更生手続きです。
会社更生手続きでは多数決原理を採用されているため、一部の債権者が反対している状況でも、強制的に債務の減額等を行い、会社の再生を実現することができます。
会社更生手続きを利用するための条件とは?
会社更生手続きを利用するためには、以下の1~5のすべての要件を満たす必要があります。
- 以下のいずれかに該当すること
・支払不能または債務超過のいずれかが生ずるおそれがあること(会社更生法17条1項1号)
・弁済期にある債務を弁済すると、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがあること(同項2号) - 更生手続の費用が予納されていること(同法41条1項1号)
- 係属中の破産手続き、再生手続きまたは特別清算手続きによることが、債権者の一般の利益に適合する場合でないこと(同項2号)
- 更生計画案の作成・可決の見込み、または更生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとはいえないこと(同項3号)
- 更生手続開始の申立てが不当な目的によるなど、不誠実にされたものではないこと(同項4号)
会社更生手続きの流れ
会社更生手続きは、大まかに以下の流れで進行します。
更生手続開始の申立て・開始決定
まずは裁判所に対して、更生手続開始の申立てを行います(会社更生法17条1項)。
会社更生の申立権がある者は、以下のとおりです。
- 株式会社(債務者)
- 資本金の額の10分の1以上に当たる債権を有する債権者(同条2項1号)
- 総株主の議決権の10分の1以上を有する株主(同項2号)
申立先は、主たる営業所の所在地や本店所在地を管轄する裁判所などから選ぶことができます(同法5条1項、2項)。
また、会社の営業所や本店の所在地にかかわらず、東京地裁と大阪地裁には常に管轄権が認められています(同条6項)。
申立てを受けた裁判所は、前述の会社更生手続きを利用するための条件が満たされていることを確認したうえで、更生手続開始の決定を行います(同法41条1項)。
同時に管財人が選任され、以降は管財人が会社の経営および財産の管理・処分を行うことになります。
債権届出期間
会社更生手続きに参加しようとする債権者は、裁判所が定める債権届出期間において、所定の事項を届け出る必要があります(会社更生法138条1項)。
債権届出期間内に届出がなかった債権については、原則として、会社更生手続きにおいて権利を行使することができません。
更生計画案の提出
債権届出期間の満了後、管財人は、債務の減額等についての詳細を定めた「更生計画案」を裁判所に提出します(会社更生法184条1項)。
なお、届出をした債権者や株主も、対抗案としての更生計画案を作成して、裁判所に提出することが認められています(同条2項)。
更生計画案の決議
裁判所に提出された更生計画案は、裁判所による形式的な審査の後、債権者・株主による決議に付されます。
更生計画案の決議は、変更を受ける権利の内容ごとに行われ、それぞれ以下の割合の賛成が必要です(会社更生法196条5項)。
①更生債権の変更について
行使可能な議決権の2分の1超を有する更生債権者の賛成
②更生担保権の変更について
(i)期限の猶予を定めるもの
行使可能な議決権の3分の2以上を有する更生担保権者の賛成
(ii)減免など、期限の猶予以外の権利変更を定めるもの
行使可能な議決権の4分の3以上を有する更生担保権者の賛成
(iii)更生会社の事業全部の廃止を定めるもの
行使可能な議決権の10分の9以上を有する更生担保権者の賛成
③株式の変更について
行使可能な議決権の過半数を有する株主の賛成
更生計画の認可
更生計画案が決議された場合、裁判所は以下の要件に該当することを条件として、更生計画を認可する決定を行います(会社更生法199条2項)。
- 更生手続または更生計画が、法令および最高裁判所規則の規定に適合するものであること
- 更生計画の内容が、公正かつ衡平であること
- 更生計画が遂行可能であること
- 更生計画の決議が、誠実かつ公正な方法でされたこと
- 持分会社への組織変更・合併・会社分割・株式交換・株式移転・株式交付を行う場合、認可決定時点でそれが可能であること
- 行政庁による許認可等を要する事項を定めている場合、更生計画の内容が、当該行政庁の意見に重要な点において反していないこと
なお、更生計画が法令または最高裁判所規則に違反している場合でも、違反の程度や更生会社の現況などを考慮したうえで、裁判所の裁量により更生計画が認可されることがあります(同条3項)。
更生計画に従った権利の変更
裁判所が更生計画の認可決定が行ったら、その時点から更生計画の効力が生じ(会社更生法201条)、債権者および株主の権利変更が行われます。
更生会社は、権利変更後の債務を計画弁済するなど、更生計画に従って会社再建を目指していくことになります。
会社更生手続きを利用するメリット
他の債務整理手続きと比較した場合、会社更生手続きには以下のメリットがあります。
会社を存続させることができる
会社更生のもっとも大きなメリットは、会社を存続させたまま財務状況を改善できる点です。
法人破産により事業をリセットするのはもったいないと考える場合には、会社更生の利用を検討する価値があるでしょう。
また、会社を存続させることにより、従業員の雇用を守れるメリットもあります。
担保権付き債権や株主権を変更できる
会社更生は、担保権付き債権や株主権を変更できる点で、民事再生よりも強力な手続きです。
権利変更の許容範囲が広い分、会社の維持・再建に当たっての選択肢が幅広く、抜本的・実効的な再建策を講ずることが可能になっています。
会社更生手続きを利用するデメリット
会社更生手続きは、株式会社の再建を抜本的に推進できる一方で、信用や費用の面でデメリットが存在します。
会社の社会的信用が低下する
会社更生の申立てが行われた場合、その事実は全国紙などで大々的に報道される可能性が高いです。
会社更生は「企業倒産」として取り扱われるため、世間に対して与える印象も悪くなります。
また、実際に権利の変更を受ける金融機関や取引先などからは、事業上の信用を失ってしまうことになるでしょう。
高額の費用が必要になる
会社更生のもう一つのデメリットは、高額の費用がかかる点です。
会社の規模・事業内容・債務の総額などによって異なりますが、裁判所に納付する予納金だけで2,000万円~3,000万円以上、それに加えて弁護士費用も数百万円~数千万円かかってきます。
非常に高額な費用が必要になるため、会社更生は実質的に大企業専用の手続きとなっています。
もし中小企業が、会社を存続させたまま債務の負担を軽減したいと考える場合には、民事再生などの利用を検討しましょう。
民事再生と会社更生の違い
会社を存続させつつ、債務の減額等を通じて会社の再生を図る手続きとしては、会社更生以外にも「民事再生」があります。
民事再生も、会社更生と同様に、多数決原理に基づいて債務の減額等を行い、会社の財務状況を改善して再生を促す手続きです。
その一方で会社更生には、民事再生にはない以下の特徴があります。
経営陣の退任が必須
民事再生の場合、経営陣が退任せずに、引き続き会社の経営を行うことも認められます。
これに対して会社更生の場合、手続きが開始した時点で、会社の事業の経営権および管理処分権が、すべて管財人へと専属的に委譲されます(会社更生法72条1項)。
それに伴い、現経営陣は必ず退任を迫られることになります。
経営陣の退任を必須とすることにより、会社全体を抜本的に改革することを目指す点が、会社更生手続きの特徴と言えるでしょう。
担保権付きの債権や株主権も変更の対象
民事再生手続きでは、担保権者には「別除権」が認められており、手続き外で担保権を実行することができます(民事再生法53条2項)。
一方会社更生手続きでは、担保権者に別除権が認められていません。
担保権付きの債権は「更生担保権」に該当し、権利変更の対象とされているのです。
また、民事再生手続きでは株主の権利が変更されることはありませんが、会社更生手続きでは、更生計画中に株主の権利変更について定めることが必須とされています(会社更生法167条1項1号)。
このように、担保権付き債権や株主権を変更できるため、会社更生は民事再生よりも強力な手続きと言えます。
会社更生を利用できるのは株式会社のみ
民事再生手続きは、会社の種類を問わず利用できるほか、個人も利用することが可能です。
これに対して会社更生手続きは、株式会社のみが利用対象とされています。
これは、不特定多数の者から出資を募ることが想定される会社(=株式会社)を抜本的に救済するという、会社更生手続きの趣旨・目的によるものです。
会社更生その他の債務整理は弁護士に相談を
会社更生は、大規模な企業が経営危機からの再建を目指すに当たって、有効に機能する可能性があります。
非常に大がかりな手続きになりますので、弁護士と綿密に打ち合わせたうえで、裁判所への申立てを行いましょう。
その一方で、会社更生は費用負担が非常に重いことから、多くの会社にとっては、会社更生以外の債務整理手続きを利用する方が適しています。
たとえば民事再生は、会社更生と同様に、会社を存続させながら債務負担を軽減することが可能です。
また、会社再建の見込みが立たない場合には、法人破産も検討すべきでしょう。
弁護士にご相談いただければ、依頼者のご状況に合わせて、どの手続きをどのように進めていくのが良いかをアドバイスいたします。
会社の経営状況が思わしくなく、債務整理をご検討中の経営者の方は、お早めに弁護士までご相談ください。