個人再生に仕事・職業の制限はある?
個人再生をするには、様々な条件を満たさなければなりません。職業に関する制限や条件があるのか?個人再生と職業の関係につ…[続きを読む]
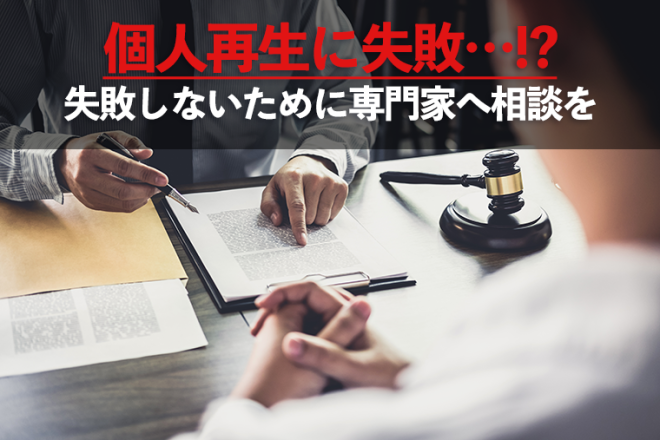
個人再生は、マイホームを保持しながら借金を大幅に減額できる可能性がある方法ですが、その手続きは必ずしも成功するとは限りません。特定の条件を満たしていない場合、個人再生手続きは失敗してしまうことがあります。
この記事では、個人再生が失敗する可能性のあるケースや、失敗した場合の影響について解説します。また、失敗を避けるためにどのような対策を取るべきかについても詳しく説明します。
個人再生の手続きにおける条件や注意点を理解し、失敗を防ぐための対策を講じることは非常に重要です。今後個人再生を検討している方は、ぜひこの記事を参考にして、適切な判断をする際の情報を得てください。
目次
個人再生に失敗するということは、個人再生の条件を満たしていないということになります。
個人再生の条件は以下の通りです。すなわち、以下に当てはまらない場合、そもそも個人再生をすることはできません。
個人再生ができるのは、住宅ローンを除いた債務の額が5,000万円以下の場合です。
これを超える借金がある場合、現実的には自己破産しか選択肢がなくなるでしょう。
また、無職であるなど、債務者本人に収入がないと、個人再生してもその後の返済ができませんので、裁判所は個人再生を認めてくれません。
正社員ではなくパートやアルバイトでも可能なことはありますが、単発または短期のアルバイトを渡り歩いているような場合は、「継続的に反復して収入を得る見込み」がないとみなされてしまうでしょう。
また、個人再生においては、減額後に支払わなくてはならない最低限度額が決まっています。
例え定期的な収入があったとしても、原則3年(例外5年)の分割払いで最低限度額以下しか支払えないようだと個人再生はできません。
さらに、小規模個人再生をする場合、債権者の半数以上の消極的同意もしくは債務総額の半数以上の消極的同意が必要とされています。
消極的同意とは「反対ではない」「異議はない」といった程度の同意です。
債権者に対して不義理・不道徳・不誠実な行為をした過去があると、消極的同意が得られない可能性があるでしょう。
なお、給与所得者等再生の場合、この条件は存在しません(債権者の同意を得ずとも手続きを進められます)。
【給与所得者等再生の条件】
以下のことが過去7年以内にある場合は、給与所得者再生が利用できませんのでご注意ください。
・破産免責(自己破産)などの確定
・個人再生手続のハードシップ免責許可の決定
・給与所得者再生の再生計画認可決定
さて、以上の条件を全て満たしていた場合は必ず個人再生が成功するのかというと、実はそうではありません。
条件を満たしていても、「棄却」「廃止」「不認可」のいずれかとなると、個人再生には失敗してしまいます。
以下、順番に解説していきます。
「棄却」とは、裁判所に申立てをしたものの、「個人再生の要件を満たしていない」と判断され、門前払いをされてしまうことをいいます。
借金総額が5,000万円以下、返済の見込みがないことが明らかなどといった既出の条件以外で棄却されるケースとしては、以下のことが考えられます。
当たり前ですが、裁判所に費用を納めなければ個人再生は開始してもらえません。
個人再生をすれば借金の大幅な減額が見込まれるので、結果的にはプラスになります。
個人再生を申し立てる前から予めお金を積み立てておき、しっかりと納めるようにしましょう。
なお、弁護士や司法書士に個人再生を依頼すれば、受任通知により債権者からの督促と支払いがストップします。
そこで、これまで返済に充てていた資金を裁判所費用として積み立てることができるでしょう。
例えば、一部の債権者にのみ返済を続けている状態で個人再生の申立てを行うと、何らかの不当な目的があると判断されて棄却される可能性があります。
個人再生には多くの書類や費用が必要です。しかし、それらを期日通りに提出しないと、裁判所が個人再生を棄却してしまいます。
棄却されずに個人再生手続きが始まったものの、途中で問題が見つかったら、個人再生手続きが「廃止」され失敗してしまう可能性があります。
個人再生手続きが廃止されるのは、主に以下のようなケースです。
個人再生の際には、裁判所に財産目録を提出します。
これに記載すべき財産を故意に記載しなかった(財産隠しをした)、または虚偽の記載をしたときには手続きが廃止されてしまいます。
弁護士に財産目録を作ってもらう際には、嘘をつかずに正直に財産の内容を伝えてください。
再生計画案を作っても、期限内に提出しなければ手続きが廃止されてしまいます。
なお、仮に提出したとしても、その内容が決議に付するに足りない、つまり「いい加減なもの」「完遂できる可能性がない」場合も手続きが廃止されます。
弁護士と連携して、実現可能な再生計画案を作れば問題はありません。
実際、弁護士が代理をしたケースでこの廃止があることはほとんどありませんので、個人再生は最初から弁護士に依頼をすることがお勧めです。
先述の通り、小規模個人再生をする場合、債権者の半数以上の「消極的同意」「債務総額の半数以上の消極的同意」が必要です。
これを満たせない場合は、給与所得者等再生か自己破産による解決を図ることになるでしょう。
個人再生手続きが廃止されずに進んだとしても、結果として再生計画の認可が受けられないこともあります。これを「再生計画の不認可」と言います。
以下のような場合、再生計画が認可されず個人再生が失敗してしまいます。
個人再生は法律に則った手続きなので、どこかに違反があると不認可となります(違反があっても、それを補正できれば問題なく認可されることが多いです)。
不正の方法とは、例えば関係者への脅迫や強要、賄賂などです。
また、裁判所に提出した書類に虚偽の記載があることが判明した場合も不認可となります。
裁判所によっては、個人再生の手続き中に「履行テスト」というものがあり、これにパスしないと再生計画の認可が下りないケースが見られます。
履行テストとは、その名の通り「再生計画通りに返済できるどうかテストしてみる」ことを指します。
裁判所側が指定した銀行口座へ、再生計画にある通りの額を毎月振り込ませることで、再生計画通りに支払いができるかどうかをテストするのです。
テストは大体6回ほど、つまり半年にわたって行われます。もしこの間に支払いができなかった場合、再生計画や申立人の支払能力に問題があるということで再生計画の認可がされません。
ちなみに、履行テストで振り込んだお金は、個人再生委員の報酬分などを差し引いて、テスト後に申立人に返還されます。
個人再生に詳しい弁護士なら、無理なく履行テストを遂行可能な再生計画となるように前もって対処してくれるでしょう。
無事に認可決定を受けたとしても、裁判所は後で認可決定の取り消しをすることができます。「債務者が再生計画の履行を怠った」「再生計画が不正の方法により成立したことが後から判明した」などのケースです。
取り消しを受けると、せっかく再生計画が認可されて減額された借金が認可前の額に戻ってしまいます。
条件を満たしていなかったり、手続中に不備が生じたりして個人再生に失敗してしまった場合、当然ですが借金は減額されません。
では、借金問題を解決する他の方法はあるのでしょうか?
他の債務整理方法としては、任意整理もしくは自己破産が考えられます。
しかし、任意整理は多額の借金を解決するには不向きな手続きであり、個人再生を考えていたならば、(借金の金額や現在の収入の状況によりますが)事実上自己破産をしなければならないケースが多いでしょう。
ただし自己破産をすると、一定額以上の財産は裁判所が処分・換価し、債権者に配当されてしまいます。生活必需品などは手元に残せますが、マイホームや高価な自動車などは失うことになるでしょう。
他にも、免責不許可事由があるなど、自己破産には注意点が多いので、弁護士に相談して個別に注意点を教えてもらいながら手続きを進めていきましょう。
個人再生が失敗する理由は非常に多く、「失敗の確率が高いのでは…」と不安に思う人も多いです。
しかし、基本的には個人再生に実績のある弁護士や司法書士に依頼をし、専門家に言われる注意事項を守るだけで成功に導くことができます。
実際、個人再生の失敗率は6%前後と言われています(司法統計による)。
反対に、隠し事をしたり、裁判所からの指示を守らなかったりすると、個人再生が失敗する可能性があります。
個人再生では、慎重に債務整理に強い弁護士・司法書士を選んで、裁判所に対しても不誠実な対応をしないようにしましょう。